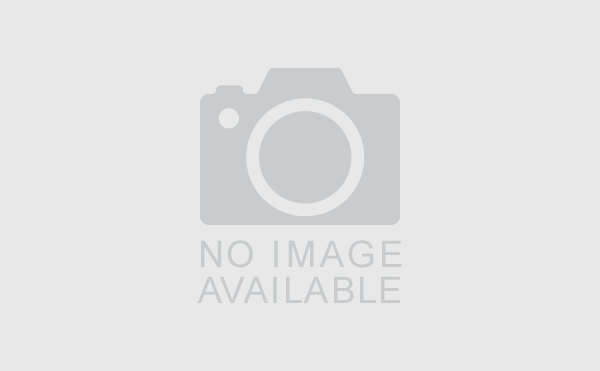二重課税防止条約(日墨租税条約)の基礎知識
はじめに
二重課税防止条約(日墨租税条約)は、同一所得への二重課税を回避し、租税回避を防止するために、居住地国・源泉地国の課税権や源泉税率の上限、二重課税の排除方法を定める取り決めです(条約:第4条(居住者)、第5条(恒久的施設=PE)、第7条(事業利益)、第10〜12条(配当・利息・ロイヤリティ))。メキシコ子会社から日本居住者への支払では、居住者証明の取得と手続を満たすことで、源泉税率が条約上限まで軽減されます。
サマリー
- 課税権の配分:配当・利息・ロイヤリティは条約で上限税率が規定(第10〜12条)。
- 適用の鍵:条約率の適用には居住者証明が必須(第4条)。支払・証憑(CFDI)の整合も必要(CFF第29条・第29-A条)。
- PEの有無:役務提供・駐在・建設工事等でPEに該当する場合、第7条の事業利益として源泉地国課税が生じ得る(第5条)。
1. 条約の基本構造
- 居住者(Residence):どの国の居住者かを規定(第4条)。二重居住時はタイブレーク・ルール。
- 恒久的施設(PE):工場・事務所・建設工事など一定要件でPEに該当(第5条)。例:長期の建設サイト、支店・営業所等。
- 所得区分の代表例:
- 配当(Dividends):第10条 源泉税率に上限。
- 利息(Interest):第11条 一般上限と一部特例。
- ロイヤリティ(Royalties):第12条 上限税率を規定。
- 二重課税の排除:居住地国側で税額控除等により調整(条約「二重課税の回避」規定)。
2. 日墨租税条約の代表的な上限税率
条文ベースの上限税率(例):
| 区分 | 条文 | 上限税率(例) | 補足 |
|---|---|---|---|
| 配当 | 第10条 | 5% / 10% | 持株割合等の要件により軽減(5%)と一般(10%)の二本建て |
| 利息 | 第11条 | 10% | 公的機関・特定債券等で更なる軽減の規定あり |
| ロイヤリティ | 第12条 | 10% | 技術料・著作権料等に適用 |
※実務適用は条文・議定書の条件充足が前提です。案件ごとに最新条文をご確認ください。
3. 条約適用の実務ステップ
- 契約確認:配当・利息・ロイヤリティ・役務など所得区分を把握。
- 居住者証明:相手先から居住者証明を取得(第4条)。
- 条文判定:上記第10〜12条等に基づき上限率を判定。
- 源泉徴収と証憑:支払時に条約率で源泉し、CFDIへ適切に記載・保存(CFF第29条・第29-A条)。
- 申告・保存:留保税の納付、契約・居住者証明・計算根拠・CFDIを保存。
4. よくある誤解と正しい理解
- 誤解:条約があれば常に0%になる。
正しい理解:多くは上限税率(例:5%/10%/10%)であり、0%とは限らない(第10〜12条)。 - 誤解:居住者証明がなくても適用できる。
正しい理解:居住者証明は必須。手続不備は条約率不適用の典型要因(第4条)。 - 誤解:役務提供は必ずロイヤリティ課税。
正しい理解:実態により事業利益(第7条)や人的役務等となり得る。
5. 事例
例:メキシコ子会社→日本親会社へ利息支払。第11条の上限10%を適用するには、事前に居住者証明を入手し、支払時に条約率で源泉、CFDIへ反映・保存。
まとめ
日墨租税条約は、配当・利息・ロイヤリティ等の国際支払で源泉税率を軽減し、課税権を整理します。居住者証明の取得と支払時の条約率判定、CFDIの整備を基本運用として徹底しましょう。
本記事は、「日系企業が安心してメキシコで事業を展開できるための知識基盤」を目的に作成しています。今後も実務に役立つ情報を発信してまいります。
関連記事
リソース
- 日墨租税条約:第4条(居住者)・第5条(PE)・第7条(事業利益)・第10〜12条(配当・利息・使用料)
- Código Fiscal de la Federación(CFF)第29条・第29-A条(CFDIの要件)